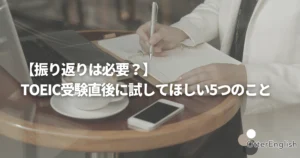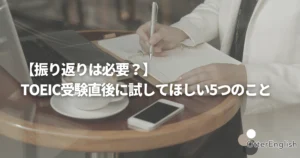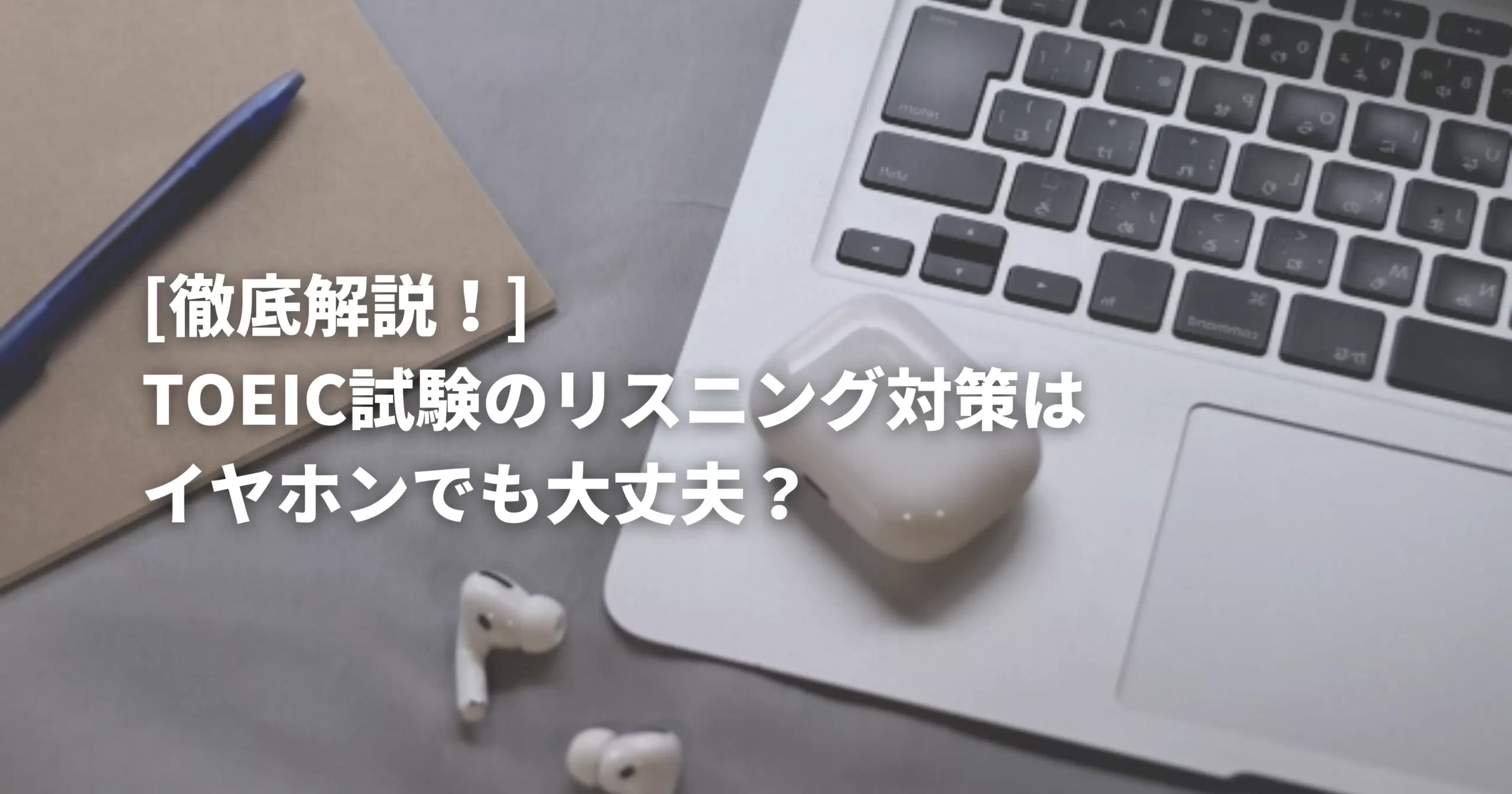TOEICのリスニング対策をする際にイヤホンとスピーカーのどちらを使うべきかは難しい問題ですよね。

僕はイヤホンを使いがちかな。楽だし。



でも、本番で音が違って聞き取りにくくならない?



確かにそうかも。
僕も何度か「リスニングスキル」と「スピーカーや会場」のどちらの問題なのかで悩んだことがあります。
実は、割れた音やこもった音を聞き取れるかどうかは、環境に加えてリスニング力も関係しています。
本記事では、リスニング対策をイヤホンとスピーカーのどちらで行うか悩んでいる方に向けて以下のような内容を紹介します。
- TOEIC試験のリスニング対策はイヤホンでも大丈夫なのか?
- それぞれイヤホン/スピーカーを使った勉強のメリットデメリット
- 環境に左右されないようになるためのリスニング対策におすすめの勉強法



以下の記事ではリスニング対策におすすめの教材を紹介しているのでぜひあわせてご覧ください。
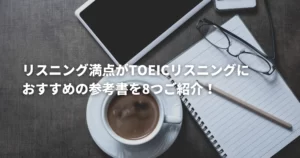
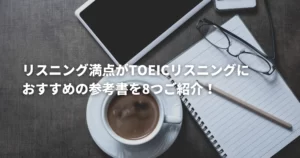
TOEIC試験のリスニング対策はイヤホンでも大丈夫なのか?
TOEICのリスニング対策には、できる限りスピーカーを使うことがおすすめです。



こんな感じでイヤホンとスピーカーを使い分けるのがおすすめです。
特に、スピーカーを使う場合は、本番環境に近づけるためにも、少し音源を遠ざけたり、薄い布を被せて音を少しこもらせたりすると良いでしょう。
本番と近い環境、もしくは本番よりも悪い環境でリスニング練習をすると、多少音が割れているスピーカーであっても音声を聞き取れるようになります。
イヤホンを使ってTOEICのリスニング対策をするメリット
ここからは、イヤホンを使ったTOEIC学習のメリットを見ていきましょう。
音がクリアで聞き取りやすい
イヤホンで音声を聞くと音がクリアでスピーカー使用時と比較して音を聞き取りやすいです。
特に、まだ勉強を始めたばかりでイヤホンを使わないと全く聞き取れない場合などは、イヤホンを使ったリスニング練習から徐々にスピーカーに移行していきましょう。
また、ディクテーションやシャドーイングをする場合も、慣れてないうちはイヤホンを使った方が難易度が低く、モチベーションを維持しやすいことでしょう。



イヤホンだと一つ一つの音がクリアに聞こえるね。
移動中でも勉強できる
移動中など、隙間時間にリスニング対策ができる点は大きなメリットです。
リスニングはできるだけ毎日音を聞いて英語に慣れる必要があり、特に忙しい方は、隙間時間の活用が必須です。
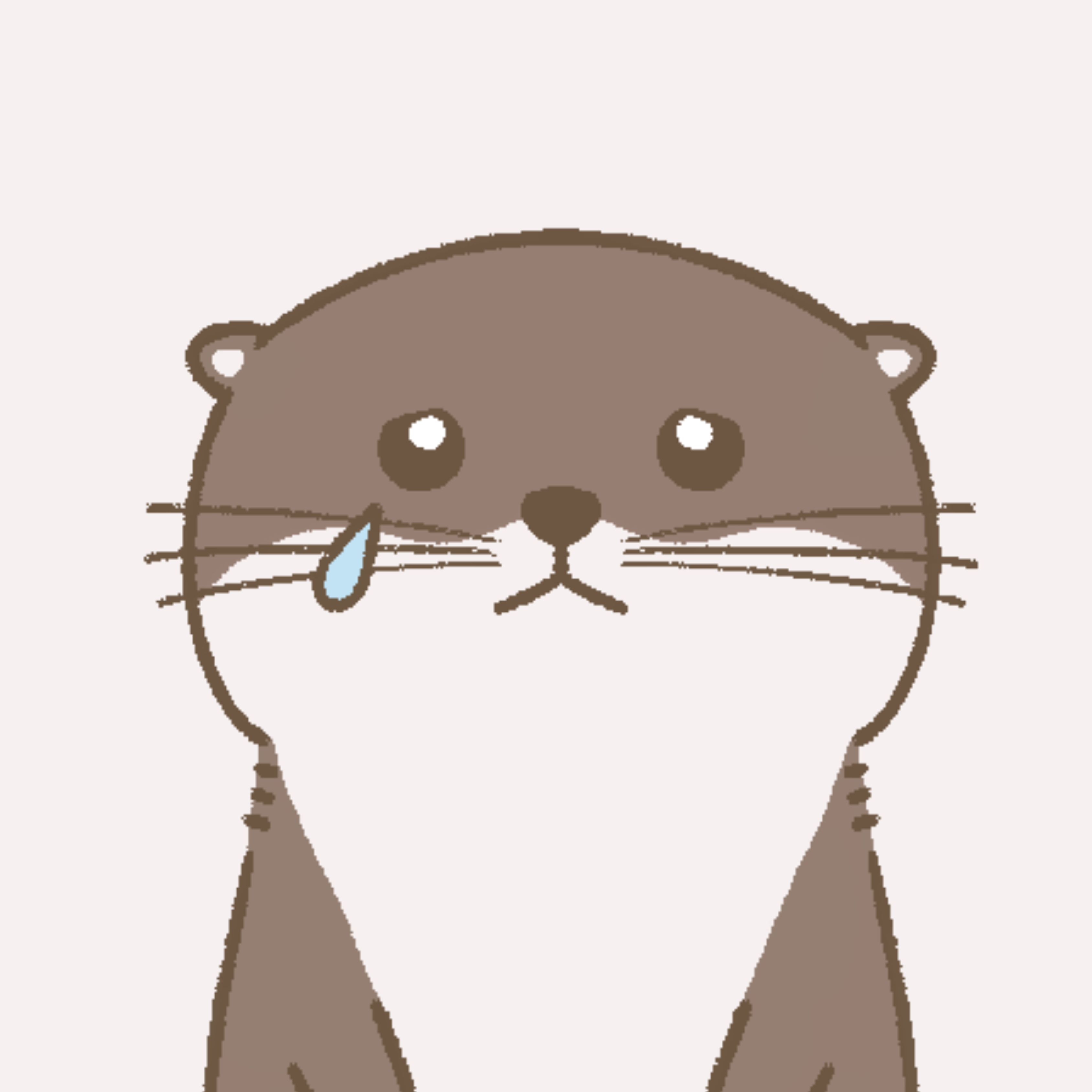
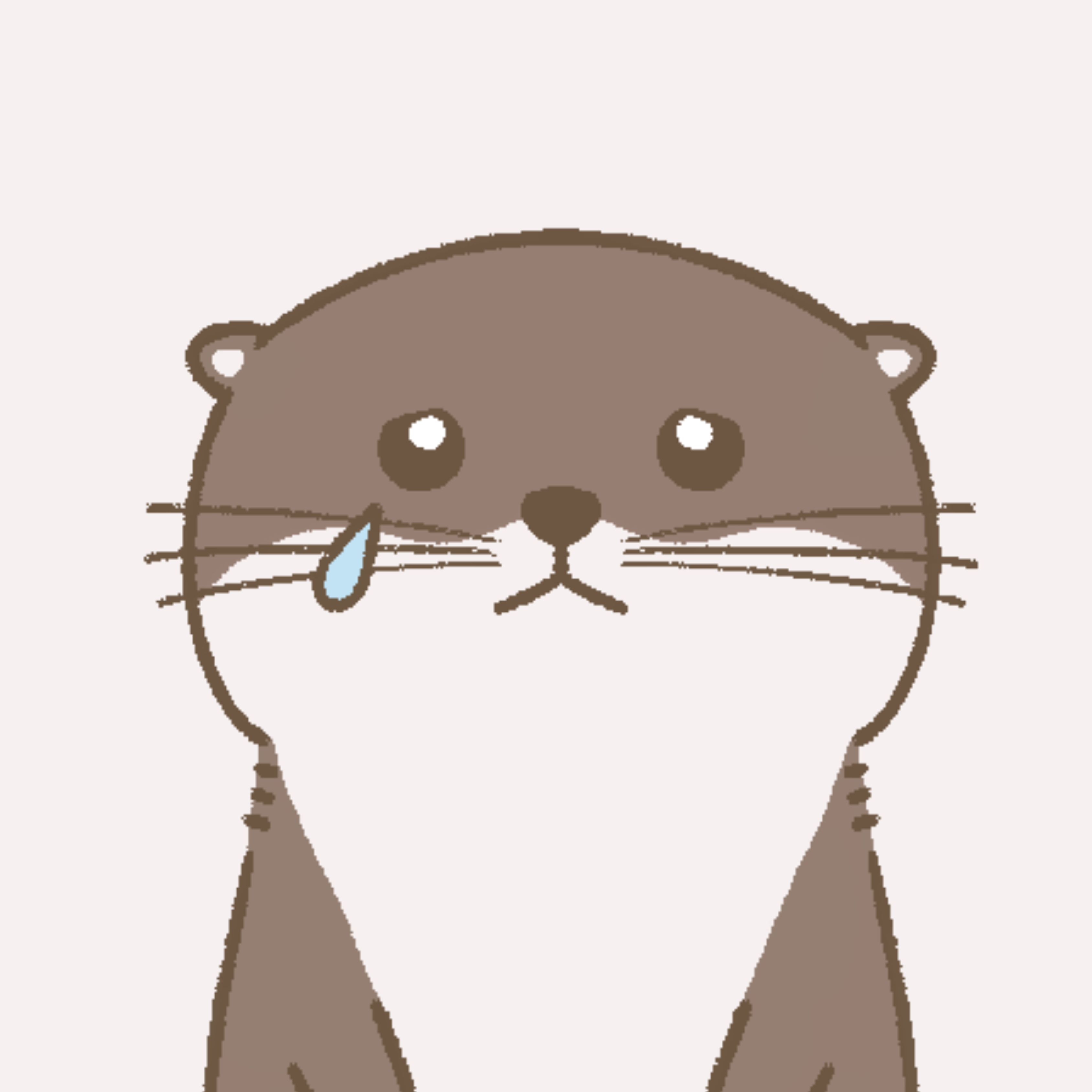
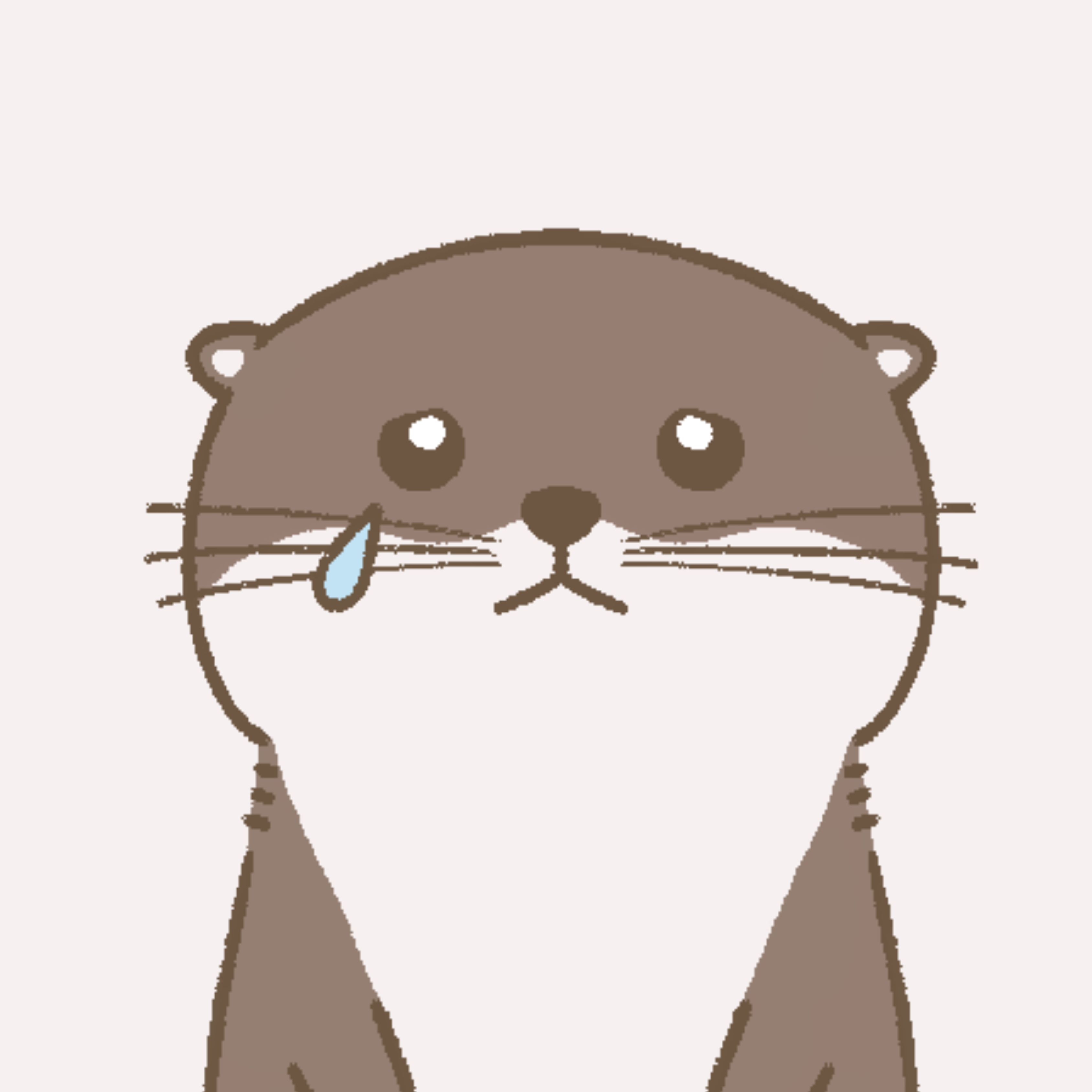
前電車で安いイヤホン使った時は、周りがうるさくて英語が聞き取れなかった…



僕はiPhoneの付属品を使ってたけど、有線だから絡まってて大変だったなあ。
同じような悩みを持っている方は、ワイヤレスのノイズキャンセリング機能がついたイヤホンがおすすめです。
僕は「AnkerのSoundcore Liberty 4」を購入してみました。


見た目も格好良く、蓋を開けたら自動でスマホと繋がるので、電車が混んでいても簡単にリスニングに移ることができました。
少し値段が高めですが、非常におすすめです。
普段使いと兼用ではなく、すでにお気に入りのイヤホンがある方はそちらをご活用ください。
イヤホンを使ってTOEICのリスニング対策をするデメリット
ここからは、反対にイヤホンを使ったTOEIC学習のデメリットをご紹介してきます。
イヤホンに慣れるとスピーカーで聞き取れない
まず、イヤホンの音に慣れると、スピーカーの音を聞き取れなくなってしまう場合があります。
特に、試験会場のリスニング音声はあまり良くないことが多いため、試験が近くなったら、できる限りスピーカーを使って音を聞くことに慣れておく必要があります。



ここは上手く使い分けが必要だね。
安いやつだと電車の中とかで使えない可能性がある
数百円くらいの安いイヤホンを使うと、電車などでそもそも音が聞こえない場合があります。
確かに、劣悪な環境でのリスニング対策は大切ですが、電車のアナウンスや電車の音が大きくて音源が聞こえないと練習の意味がないですよね。
本番でも、そもそもリスニング音源が聞こえない場合は席を移動したり、スピーカーを調整してもらったりできます。
そのため、可能であればノイズキャンセリングがついたイヤホンで集中できる環境を作ると良いでしょう。
スピーカーを使ってTOEICのリスニング対策をするメリット
ここからはスピーカーを使ったTOEIC学習のメリットをご紹介していきます。
実際の試験環境に近づけられる
スピーカーを使ったリスニング練習を行うことで、実際の試験環境に近づけることができます。
余裕があれば、薄い布を被せて音をこもらせてみたり、スピーカーを自分から遠ざけて、あえて小さめの音で聞いてみるのも良いでしょう。



本番で音が聞き取りにくかった場合の対策になります。
TOEICの本番が近づいた場合は、以下の項目に意識してみてください。
・試験時間と同じ形式で2時間続けて問題を解く
・過去に練習した時間配分を意識する(特にリーディング)
・スピーカーを使って本番の空気感に近づける



家にスピーカーがない人はスマホのスピーカーを使おうね。
耳が痛くならない
長時間イヤホンをつけていると耳が痛くなります。
特に、ディクテーションやシャドーイングを行う際は、1時間〜2時間以上イヤホンをつけっぱなしにすることも珍しくないと思います。
スピーカーはイヤホンのように耳につける必要がないため、耳が痛くなりません。
そのため、耳が痛くなったと感じている方は、できる限りスピーカーが使える時はスピーカーを使うことをおすすめします。
スピーカーを使ってTOEICのリスニング対策をするデメリット
それでは、スピーカーを使ったTOEIC学習のデメリットをみていきましょう。
外出中は使えない
周りの迷惑になるため、外出中にはスピーカーは使えません。
特に、通勤時間や通学時間にしか時間を確保できないような方はイヤホンを使って学習することが必要となります。
休みの日に、スマホのスピーカーを使った勉強ができるように意識しましょう。



僕は基本イヤホン、講義がない日はスピーカーを使ってました。
イヤホンよりも音が聞き取りにくい
スピーカーはイヤホンよりも音が聞き取りにくいです。
そのため、まだ勉強を始めたばかりでイヤホンを使わないと全く聞き取れない方は、イヤホンを使ったリスニング練習から徐々にスピーカーに移行しましょう。
練習でイヤホンばかり使っているとTOEIC本番で困る場面
ここでは、イヤホンを使って勉強をしているとTOEIC試験本番で困ってしまうことをみていきましょう。
試験会場が大きい
まずは試験会場が大きく、音が反響してしまう場合です。
1つの会場に集まる受験者数も多いため、受験者が立てる音もリスニングに影響を与えてくる可能性があります。



貧乏ゆすりの音とか気になりますよね。
TOEICではリスニング開始前に必ず音声の確認テストが行われるため、もしも音が小さいと感じたら恥ずかしがらずに挙手して試験管に伝えましょう。
スピーカーが離れている
次にスピーカーの位置が離れている場合です。
会場の一番前にスピーカーが置かれていて、前方では音声が聞き取りやすく、後方では音声が聞き取りにくいパターンです。
空調がうるさい
空調がうるさい場合もリスニングに影響が出ます。
試験開始後に慌ててしまわないように、試験会場に入った時点で空調の稼働具合を把握し、覚悟しておきましょう。
貧乏ゆすりや鼻を啜る人がいる
僕もたまに遭遇しますが、試験会場でリスニング中に「貧乏ゆすりをする人」や「鼻を啜る人」がいます。
ちょうどリスニングで答えの部分が読み上げられている時に限って音が気になることってありますよね。
リスニング力を身につける以外の対策は難しいため、この後紹介するリスニング対策におすすめの勉強法を使って対策をしていきましょう。
TOEICリスニング対策におすすめの勉強法
リスニング対策におすすめの勉強法は下記6つです。
・TOEIC用の単語帳を使って語彙力を増やす
・TOEICのリスニング参考書を勉強に使う
・TOEICのリスニング問題の解き方のコツを身につける
・ディクテーションやシャドーイングをする
・英語を毎日聞く機会を作る
・同じ教材を繰り返し使う
リスニング対策は、TOEIC用の単語帳を使って語彙力を身につけることや、解き方のコツを身につけることが大切です。
また、本番のリスニング環境が悪かった場合に備えて、ディクテーションやシャドーイングを通して基礎的なリスニング力を身につけておきましょう。



できるだけ毎日英語を聞く機会を作りつつ、本番で力を発揮できるように頑張りましょう。
詳しいリスニングの対策法は、下記記事をご覧ください。
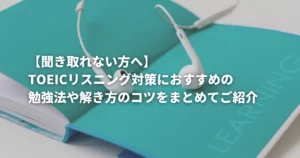
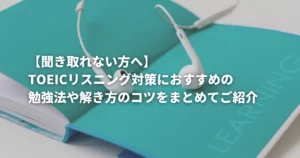
リスニング対策におすすめのアプリ・教材
それでは、リスニング対策におすすめのアプリと教材を紹介します。
TOEICのレベル別おすすめ参考書は以下にまとめているので、あわせてご覧ください。
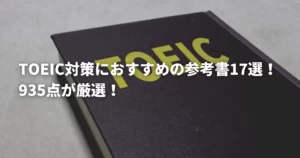
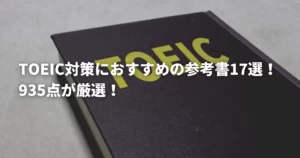
スタディサプリ(TOEIC対策コース)
スタディサプリ(TOEIC用)は、TOEICに特化した対策ができるアプリです。
隙間時間を使ったTOEIC対策や、実践形式の問題への回答を通して、効率的に学習できます。
アプリは月額制で有料ですが、短期間で効率よくスコアを上げたい方、まとまった時間が取れずに隙間時間で着実に勉強を進めたい方にはおすすめです。
また、1週間の無料体験期間も設定されているので、実際に有料コースに移行する前に、ご自身の勉強スタイルと合っているかを確認することもできるので、ぜひ試してみてください。
\ 1週間無料体験!/
Santa
Santaは、600万人の利用者がいるAI学習アプリで、学習レポートをもとに専用のおすすめ学習に関する提案を受けることができます。
診断テストからTOEICスコアを95%の精度で予測し、予測スコアの分析をもとに目標スコアとの差分を明確にすることができます。
・単語学習
・リスニング
・リーディング
の全てに対応できるため、TOEICスコアで伸び悩んでしまっている場合やこれから短期間で高得点を取得する必要がある場合はぜひ試してみてください。
ちなみに、僕がSantaの無料のTOEICスコア診断を受験した結果と受験の手順はこちらにまとめています。
アプリダウンロードから受験、結果の確認まで10分くらいで終わるので、今後の学習計画を立てるためにも、隙間時間にぜひ自分のスコア予測を確認してみてください!
\ AIを使ったTOEIC学習!/
特急シリーズ
おすすめポイント
◆各Partに特化した形で対策できるので形式に慣れることができる
◆問題数が多い
◆解説が分かりやすい
各Partの対策でもご紹介している特急シリーズですが、各Partの問題形式に慣れたり、苦手な部分を強化したりするために使うことができます。
全くTOEICを受けたことがない方やこれから本格的に対策を始める方は特急シリーズを一通り解いて問題の形式に慣れることをおすすめします。
僕も、最初は特急シリーズを使って、Partごとの癖や解き方を勉強しました。
特急シリーズの説明も含めたPartごとの勉強法は別記事でご紹介しているためぜひご覧ください。
公式問題集
現時点での最新の公式問題集は11です。
おすすめポイント
◆TOEICの公式が出している問題集で、本番と問題が近い
◆リスニングのナレーターが本番と同じ
◆新しい傾向に合わせた対策ができる
困ったらとりあえずこれから始めてみましょう。
2回分の模試が収録されています。
そのため、もしも本問題集を解いたことがない場合はぜひ本番前に解いて試験に慣れることがおすすめです。
このTOEICの公式問題集は定期的に新しいものが出版されるので、最新のものから使っていくようにしましょう。
公式問題集は本番に近い問題が収録されており、力試しや本番直前に試験形式で実力を確認するのに効果的なので、ぜひ使ってみてください!
まとめ
本記事では、TOEICのリスニング対策にイヤホンとスピーカーのどちらを使うと良いのかをそれぞれのメリットデメリットも含めご紹介しました。
本番に近い環境を作って練習を行うことに加えて、リスニングの解き方のコツや基礎的なリスニング力を身につけることが必要になります。
ぜひ、TOEIC本番で実力を発揮できるように今回紹介した内容を試してみてください!
また、これからどんどんスコアを伸ばしていきたいと思っている方に向けて、TOEIC後に試して欲しいことをまとめたので、下記記事をぜひブックマークして、試験後に見直してみてください!